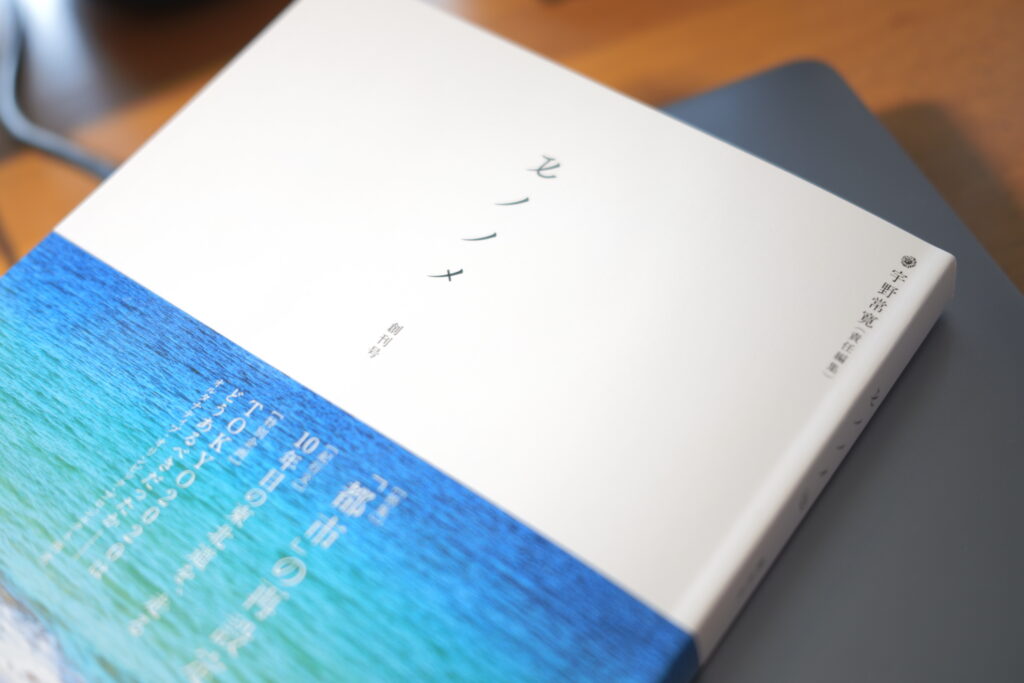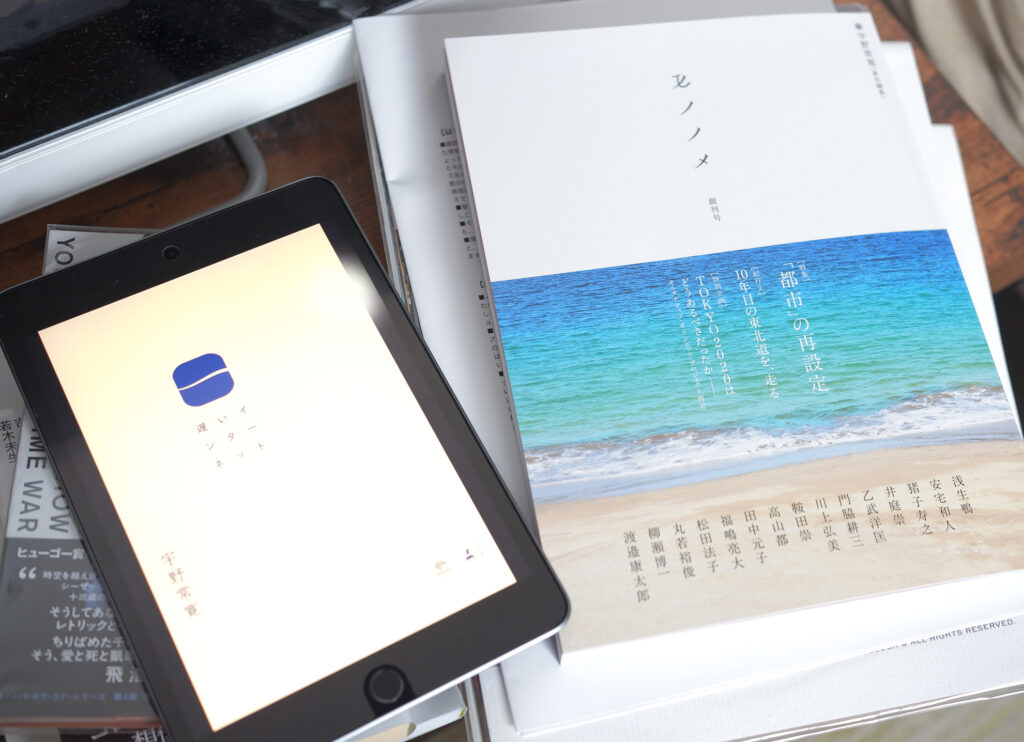
『遅いインターネット』(著:宇野常寛)という本がある。
昨今、インターネットを誰もが利用することができるようになり、誰でも簡単に最新の情報へアクセスできるようになった。
そしてSNSの普及によって、誰でも最新の情報にアクセスできるようになった。
誰もが便利だと思う世の中になっているとは思うけど、
『遅いインターネット』ではそういう世の中をちょっと異なる視線で見てくれている。
情報が早すぎることって本当にいいことなのか?
今ではテレビ番組でも、何かの報道に関する情報はSNSから募り、
なるはやでその情報を投稿しているユーザーに許可を取って、そのまま番組で流すことがある。
でもそれって本当なの?って疑いはありえると思ってる。
情報のプロ(ここでは定義はザックリする)ではないイチSNSユーザーが例えば映像や画像を加工して流していました、ということだって可能性はある。
早いことに釣られてそのまま信じてしまうことは危険だし、
そういう早とちりで痛い目に遭う例は少なくないはず。
早すぎる情報ほど正確である可能性が下がっていくと思う。
情報をより咀嚼し、より深く考察されたものが世に出る形になるとどれだけ良いのだろうか。
速報の存在は大切である、ただ、それをよく考える時間を取る必要がある、
という意識であるともっと正しく世の中が見えるのかもしれない。
この雑誌『モノノメ』はその想いを反映した雑誌となっている。
編集者の意思を尊重し、雑誌の中身についてはここでは触れない。
だが、ゆっくりと世の中を歩くことができるような一冊。
世の中で起きたニュースを1つ思い浮かべてほしい。
そのニュースが起きた時点、最初だけしか自分は知らない、ということは多いのではないだろうか。
そのニュースの「いま」はどうだろうか?
起きたときだけは認知できるが、情報を繋がりのある線として捉え続けてみてはどうだろうか?
いつもSNSを見て情報を得たり、テレビの速報に一喜一憂するだけでない、
この一冊で「新しい情報」を体感できると思う。